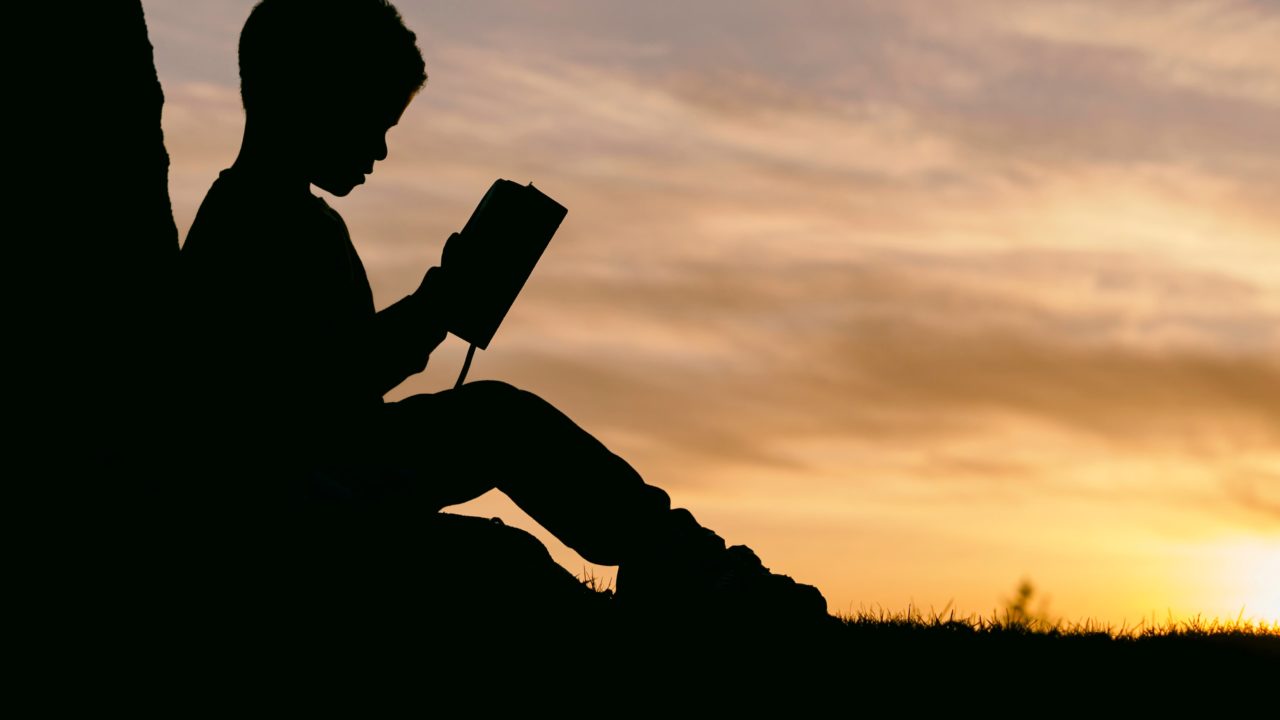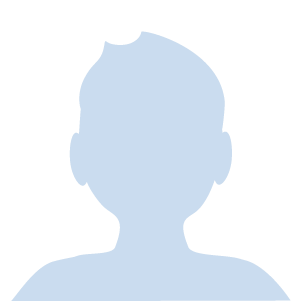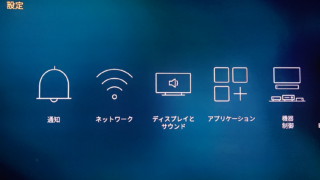お子さんの学費って小学校から大学まで含めるとかなりの額かかりますよね。すべて公立だと800万円すべて私立だと2200万円必要と文部科学省の調査結果も出ています。その中で一番ウエイトを占めているのが大学です。大学入学となると入学金、授業料など金額も一気に跳ね上がります。普通のサラリーマンだと家計は火の車になってしまいます。
そんな事にならない様に皆さんは貯金をしたり、学資保険に入ったりいろいろと準備をされると思います。でもどんな方法で教育資金を貯めていくのが一番いいんだろう?どうせ貯めるんだったら増やすことはできないのかな?と思う方も少なくないのではないでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えするべく、おすすめの教育資金の準備方法をご紹介します。具体的に申し上げるとその方法はつみたてNISAです。
まとまった学費を一度に出せる方はこの記事はあまり参考にならないと思います。お子さんが生まれてから大学に入るまでの間にこつこつと貯めていきたい方には、その時間の経過を味方にして元本に加えてボーナスを手に入れてみませんか。この記事は2回に渡って教育資金の準備方法をご紹介したいと思います。今回は学資保険のデメリットについてです。
定番の学資保険はどうなの?
昔から子供が生まれると学資保険に入るのが当然の様に思われている部分もあるんじゃないでしょうか。生まれてからすぐに積み立てて、一番お金がかかる大学入学に合わせて準備するという方が少なくないのではないでしょうか。学資保険だったら積み立てた元本より増えるし、万が一親が死んだ時も保証されるし安心ですよね。
結論から申し上げますと学資保険を教育資金にすることは微妙です。理由は下記のとおりです。
- 保険会社が経営破綻した際に元本割れのリスクがある。
- 途中解約すると元本割れする。
- 満期時に元本割れする事がある。
- 資金拘束時期が長い割に利回りが低い。
では実際に順番に検証していきましょう。
保険会社が経営破綻した際に元本割れのリスクがある。
学資保険を加入している保険会社がつぶれてしまったときは保険金はどうなるのかご存知ででしょうか。
下の保険会社は1997~2008年に実際に経営破綻した保険会社です。
これらの会社のほとんどは外資系の生命保険会社に名前を変えています。
実際は買収や合併となるケースも多いので保険も引き継がれる事が多いです。ですがその際に契約条件が変更される事もあります。また破綻した保険会社に誰も引き取り手がいない場合は破綻として処理される事になりますが、その場合は保険業法により積立が義務付けられている責任準備金から支払われる事になります。その場合は保険金の90%を限度に支払われる事となります。
必ずしも90%を補償してくれるわけではありません。90%を限度にですからそれより下回るケースも考えられます。
途中解約すると元本割れする。
学資保険は途中解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)としてお金が戻ってきますが、支払いしたお金がそのまま戻ってくるわけではありません。
加入している保険を解約した事がある人はどれくらいいるかご存知でしょうか。生命保険に関する平成30年の全国調査結果によると、全体の9.2%の方が解約・失効を経験しているという調査結果が出ています。<平成30年度 生命保険に関する全国実態調査 生命保険文化センター より引用 >
解約・失効した人の解約返戻金の使途はどの様なものでしょうか。上位3つは次になります。
1位 生活費にあてた 24.8%
2位 預貯金に預け替えた 21.5%
3位 他の生命保険の掛け金にあてた 15.8%
おそらく解約された方も好き好んで解約されたのではないと思います。
子供が生まれてから大学までの18年間には様々なイベントがあったり、不況になったりして減給するかもしれません。それでも絶対に解約はしないから大丈夫という方は良いと思いますが、途中解約した時点でペナルティーとして罰金を取られるのはリスクと考えて良いでしょう。
加入する保険によっては解約返戻金の範囲で貸付してくれるものもありますが、借りると当然金利がつきますのでその分を多く支払う事になります。
満期時に元本割れする事がある。

学資保険には「貯蓄型」と「保障型」の2つのタイプがあります。
貯蓄型はシンプルに教育資金を貯めるタイプ
「貯蓄型」は教育資金を貯める事に重点をおいたもので、保障等は最低限のものになったシンプルなタイプとなっています。こちらのタイプは返戻金と言われる満期になった時に受け取れる金額は多く元本割れするものは少ないです。
保障型は万が一のけが・入院に備えるタイプ
「保障型」は教育資金を貯める事に加えて、お子様がけがや病気で入院した時に保険金がでる医療保障がプラスされている商品です。その分満期時に受け取れる返戻金は少なく、元々元本割れしているものもあります。
【ケガや病気は他の保険や自治体の助成でカバーできる】
貯蓄型はまだ払い込み金額に対して多くの返戻金を受け取れますが、保障型の商品は最初から元本割れが確定しています。その分医療保障を受ける事ができますが、他に医療保険に加入されている方や会社で加入している保険などでカバーできる方もいると思います。また乳幼児~中学位までは医療費の補助を行っている自治体も多いと思います。一時的に支払いは発生しますが、あとで補助金としてお金が返ってきます。
【今後景気が良くなると銀行預金の方がプラスに?】 今はマイナス金利と言われる金利が低い時代ですので、銀行に預けていても金利が0.001%とほとんど増えないですよね。学資保険もお金を預かって運用するスタイルですので金利の影響を受けます。ですからマイナス金利は学資保険にとっては、正にマイナスとなります。
ほとんどの学資保険は契約時点での固定金利を採用しています。今は一番低いといっても過言ではないはずです。年利に直すと高いものでも0.3%程です。ひと昔前の金利が高かった時代は良かったんですけどね・・・例えばこれから景気が劇的に良くなって銀行の金利が3%になったとしましょう。それでも学資保険の金利は変わらず0.3%のままです。
今後の日本の経済状況ですと一気に好景気になる事は少ないと思いますが、可能性はゼロではありませんね。
資金拘束時期が長い割に利回りが低い。
学資保険は生まれてから10歳~18歳位までの間でかける方が多いと思います。それだけの長期間資金を拘束されてしまいます。その期間ずっと払い込み続けて解約もしなかったごほうびとして、返戻金としてお金をもらえる訳ですが、どのくらい増えるものなんでしょうか。払い込んだお金に対して増えたり減ったりした金額のをパーセンテージで表したものを返戻率(へんれいりつ)と言います。各保険会社の商品を比べてみました。
各保険会社の返戻率
| ソニー生命 学資保険(無配当)Ⅲ型 |
105.5% |
|---|---|
| 日本生命 こども祝金なし型 |
104.0% |
| 明治安田生命 積立学資 (21歳満期) |
105.8% |
| アフラック 夢見るこどもの学資保険(10歳払済) |
98.1% |
| フコク生命 みらいのつばさJ型 |
105.5% |
| かんぽ生命 はじめのかんぽ |
97.5% |
上の表はランキングではなく「学資保険」と検索して出てきた順に並べてみただけなのですが、300万円を積み立てる設定で試算しました。会社によって積立金額の設定などを統一できませんでしたので同条件とはいえないですが、ここで問題としているのは各保険会社の比較ではなく「最高でどのくらいの返戻率になっているか」です。
【総額の利率ではなく年率にすると0.58%実際は0.32%】
一番多いもので明治安田生命の105.8%です。この保険はトータル300万円受け取れるもので支払いは2,835,538円となります。ですので掛け金以上の保険金を受け取れるのでお得と言えます。しかしこれは払い込み総額に対してどれくらい増えたかの割合です。これを年利にしてみるとどうなるのでしょう。下記の計算式で計算してみます。
収益 ÷ 払い込み総額 ÷ 払い込み期間 × 100
収益は300万に対して2,835,538円の支払いでしたのでその差額の164,462円です。
払い込み総額が2,835,538円です。この保険の払い込み期間は10年ですので10です。これをあてはめると
164462 ÷ 2,835,538 ÷ 10 × 100 = 0.58%
年利0.58%となります。ただ、この保険の払い込みは10年で終えますが実際にもらえる時期は18歳からですのでその時期を含めると18年間の年利は0.32%となります。それでも最近(2020年)の定期預金で年利0.20%ほどですのでそれよりは優秀と言えます。
はいお得になります。ただし学資保険は途中解約すると元本割れする可能性が高いですが、定期預金は元本割れする事はありません。その辺のリスクを考慮すると0.1%の年利の差は微妙ですね。
学資保険のメリット
ここまで学資保険についてデメリットばかり並べてきましたが、もちろんメリットもあります。例えば下記の様な事です。
- 解約すると元本割れするので強制的に資金を貯める事ができる。
- 銀行預金よりお金が増える。
- 税金の控除がある。
- 契約者が死亡、高度障害を負った時に払い込み免除。
①②については本記事でも紹介したのでお解りだと思います。
③はサラリーマンの方でしたら年末調整時に「生命保険料控除」として所得税や住民税より控除されますのでその分還付金として戻ってきます。控除額がだいたい住民税で4万円位ですから住民税と併せて実際の還付金は6000円~7000円位の方が多いのではないでしょうか。
④については契約者が死亡もしくは高度の障害を負った場合についてはその後の月々の払い込みは免除され保険金受取時期に満額受け取れる様になっています。
この様な点も考慮してやっぱりうちの場合は学資保険があっているという方もいらっしゃると思います。しかし少子化が進み一人当たりの教育資金も年々上がってきています。またインフレのリスクもあります。そういった事に備えて少しでも増やしたいと考えている方はぜひ次回の記事をご覧ください。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。